
皆さん、こんな場面に遭遇したことはありませんか?
「Aさん、ニンチさんだから・・・」
「Aさん、最近、ニンチが入ってきたよね・・・」
「Aさん、最近、ニンチが進んだよね・・・」
認知症を「ニンチ」と略し、平気で使う行為・・・。
残念でなりません。
軽度認知障害の方に対して、
「最近、ニンチが入ってきた・ニンチが進んだ」
と言うのは、決して適切な言葉遣いとは言えません。
国語辞書によると「認知(ニンチ)」とは、
1.ある事柄をはっきりと認めること
2.知識を得る働きの総称
という意味になりますので、
「ニンチが進んだ」→認知症の初期症状が出現し始めた(×)
「ニンチが進んだ」→最近、認知機能が適切な状態にある(○)
と解釈するのが本来の読み解き方でしょう。
平気で使っている本人にとっては、何気ない一言かもしれませんが、
不適切で、とても恥ずべき言葉だと思います。
専門性の有無と問わず、まだまだ病院・施設・地域の中で
まだまだ多く聞かれます・・・。
私たちは、専門職らしく、適切な言葉を使い、
周囲を巻き込んでいくことが大切であると思うのです。
小さなことからコツコツと。
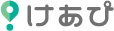
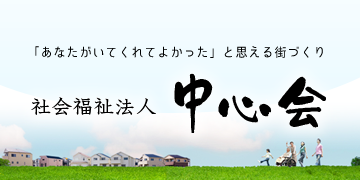


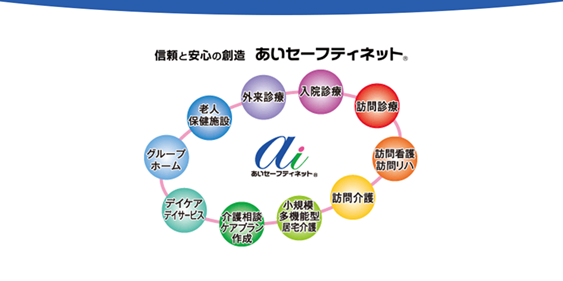



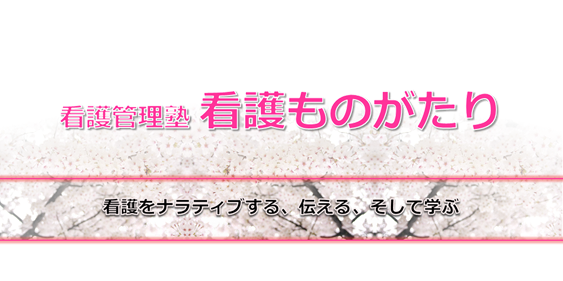



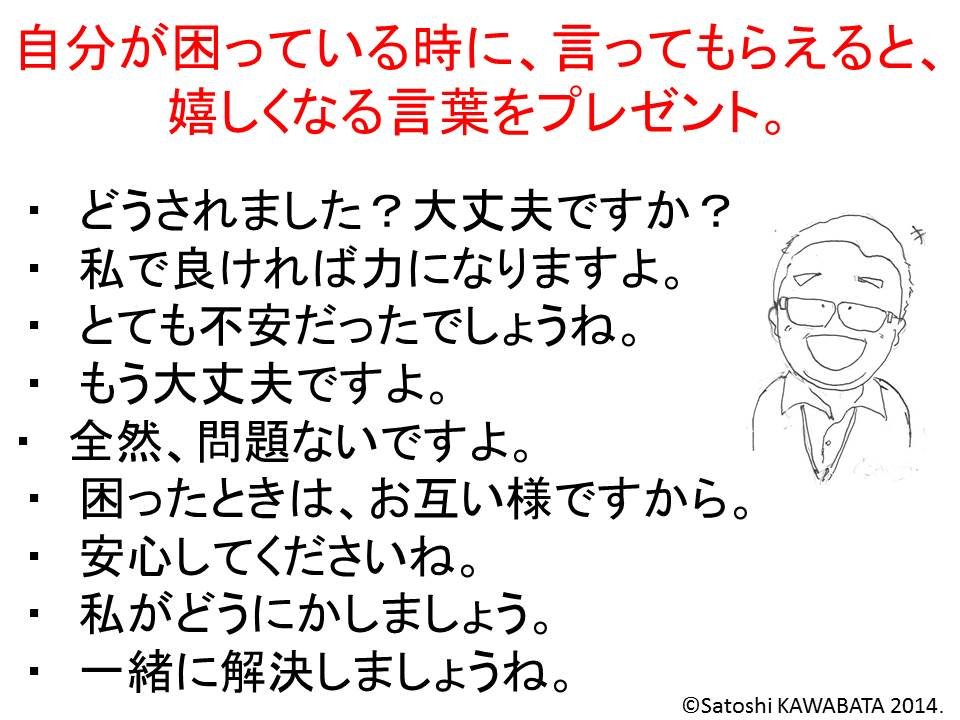



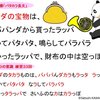









川畑先生に、同感です。
何故でしょうか…
全国的にでしょうか…
略語を勘違いしていますよね。
様々な職種の実習生の受け入れをしている当職場においても変な捉え方をされては困るなぁ。と、苦い思いをしてしまいました。
コツコツと向き合いたいと思います。
先日、あるご利用者の施設サービス計画書に目を通していると、その内容の一部に「認知面を改善する」と記載してありました。???。
正しくは「認知症の周辺症状を改善する」と表現するのでしょう。
正しい表現ができない事は、そのスタッフの個人的な要因によるものもありますが、それだけではないのでしょうね。
適切に表現するための正しい知識や考え方をもっていない。つまり、それらを身に付けるための教育を受けてこなかった。教育的要因。
また、語彙力が弱くなり、感覚的な表現が多くなった時代を生きてきた。社会的要因。
それと、そんな気になる表現が許されてしまっているかのような職場の雰囲気。環境的要因。
あと、ご利用者により良いサービスを提供するために、スタッフや職場を良き方向に導くべき管理者・指導者の能力。管理的要因。などなど。
様々な要因があるはずで、その人個人の能力やモラルといったものに解決策を見いだそうとしても、ちょっと無理があるのかもしれません。
自分がご利用者に提供したいケアやサービスを、スタッフにどう伝え実践してもらうのか。
管理者・指導者としての自分自身の評価を、スタッフのご利用者への言動にみることができるのかもしれません。
ご利用者を、『ニンチさん』なんて呼ぶ事は、ご利用者の尊厳を守る意味で、絶対にあってはならない事です。
しかし、「ニンチが入ってきた」「ニンチが進んだ」は、適切な表現がなされていない事については残念ですが、日々のケア実践を通して、ご利用者の状態に何かしらの変化を感じている点は、少し掘り下げて確認してみたいですね。
認知症の周辺症状について、過去と現在の状態を比較して、『入ってきた』『進んだ』と捉えた具体的な変化は何なのか。
『どうしてそう思ったの?』と質問してみたいものです。
そして、『その事に気付けたあなたは素晴らしい。』と誉めてあげたいですね。
ただし、『認知』の言葉の意味を調べてもらうなどして、専門用語を適切に使えるような働きかけを、忘れないようにしなければいけませんが。