
病院や施設の専門職である看護・介護・リハビリスタッフの申し送り等で、
「不穏」という言葉が乱用されていないでしょうか?
「Aさんが不穏なので、気を付けてください。」
「不穏だったので~できませんでした。」
「今日は、ずっと不穏なので~。」
確かに、「不穏状態」では、ケア負担度が高くなりますが、
現実には「不穏状態」が、予測不能で、意味もなく突発的に起こり、何の手立てもなかったかのような扱いをされていないでしょうか?
ちなみに、私は「不穏状態」を「自己解決的行動」と捉え、4段階で区分けしています。
①ご本人に何らかの「不安」が起こり、
②スタッフの対応の遅れや不足が「不満」となり、
③それらの積み重ねが「不信」へと変わり、
④どれだけ言っても伝わらないものだと考え、自らの力でどうにかしようと決心し、混乱し、穏やかに過ごせなくなる「不穏状態」。
「不安」⇒「不満」⇒「不信」のステップを踏まなければ「不穏状態」になる機会はないのです。
「不穏」なのかその前の段階なのか?しっかり分析して使ってほしい言葉です。
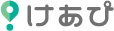
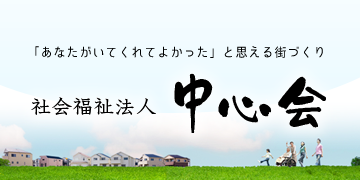


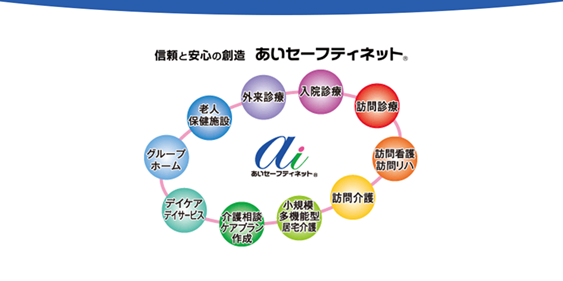



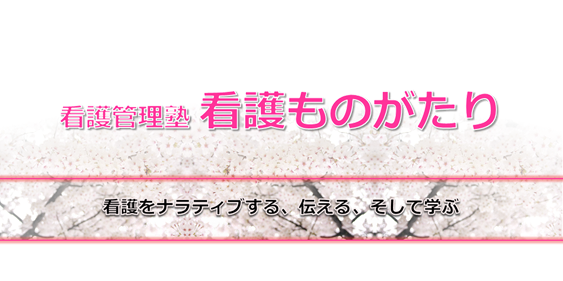







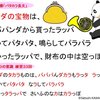









~レシピを読みながら考察~
私たちが、①不信を招いた原因や理由をイメージできるだけの精神的余裕を持ち続け、②そこに至るまで放置しないこと、にもっと力を注ぎ、穏やかな生活を支援していければ、「不穏」という言葉を安易に使うことは無くなるかもしれませんね。
「不穏」。私たち介護の現場でよく交わされる言葉であり、介護する側からの都合のよい言葉ですね。医療の現場では、なんとも説明のつかない「不定愁訴」といったところでしょうか。どちらも本人様からすれば誰にも苦しみや悲しみを理解してもらえずに辛いものだと思います。不穏に困ったと考える前に何故そのような行動をとられるのかを考えてお互いに良い関係の中で過ごしていきたいです。