
「お風呂に行きますよ」っといって、
スタッフが、Aさん(アルツハイマー型認知症の方)と一緒に居室を出る。
30mほどの廊下をゆっくり歩きながら、脱衣所に到着。
スタッフが当たり前にように、Aさんの
服に手を掛け、Aさんのボタンを外そうとすると・・・
「何ば、すっとか!!(何をするの!?)」
とAさんの拒否的態度。
スタッフは「・・・?」「お風呂ですよ!脱ぎますよ。」
Aさんは、「よか。入らん。(いいえ結構です、入りません)」
スタッフは「今日は、お風呂の日って言ったでしょ。」
Aさん「よか、汚れとらん(いいえ結構、汚れてませんので)」
スタッフは「何を言うんですか?2日前も入ってないでしょ!?」
Aさん「よか。」
こんな押し問答を見ていると、とても悲しくなります・・。
周辺症状製造者は、認知症の事を知らないスタッフ自身で、
そんなスタッフこそ、「認知症に対して、認知症」なのです。
模範解答は、下のコメントで紹介・解説したいと思います。
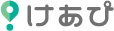
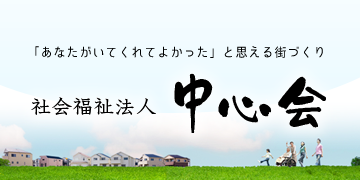


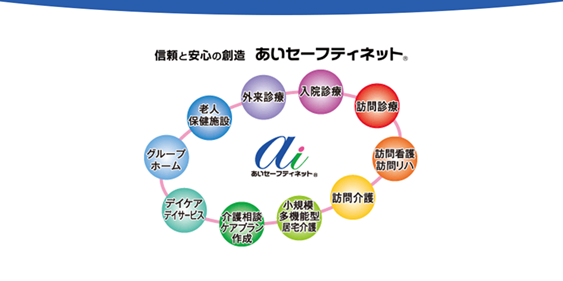



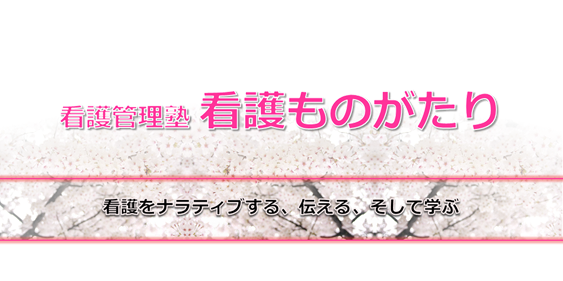



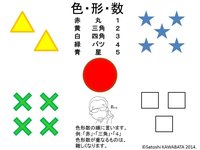



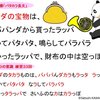









今回のケースは、海馬が正常に機能せず、短期記憶障害がある
アルツハイマー型認知症のAさんです。
(難聴や睡眠障害時でも、類似症状が出現する恐れはあります。)
通常、アルツハイマー型認知症の場合、95%は、海馬から障害が始まります。
海馬の障害=短期記憶障害ですので、数秒~数十秒前の体験を、忘却し、
すっかり忘れます。何の手がかりも、ヒントも思い出しませんので、
本人にとって「忘れる=無かった」こととなります。
今回のケースでは、廊下を一緒に歩いている間に、
お風呂に関する話をして、記憶を留めておくことが必要なのです。
「今からお風呂に行きますけど、お風呂は熱いのが好きですか?」
「若いときは、温泉には良く行かれてましたか?」
などで、記憶をアシストするのです。あとは実践あるのみ!
まとめ
一次記憶を二次記憶に固定化できないのであれば、
一次記憶を忘却しないように話をつなぐ。
こういう場面、ありますね。利用者さんがどんどん落ち着かなくなり、拒否が強くなる。
『周辺症状製造者は、認知症の事を知らないスタッフ自身で、
そんなスタッフこそ、「認知症に対して、認知症」なのです。』
・・・名言ですね(笑)。
ちょっと焦点はずれるかもしれませんが、先日、似た場面を見かけました。
歩行の不安定な方が、シルバーカーを押して歩いていると、それを目にしたスタッフが
「Bさ~ん!危ないから座ってて下さい。さっきも言ったでしょう。」と・・・。
Bさんは認知症で、さっき言ったかもしれないけど忘れてしまうんですよ。スタッフにとっては2回目かもしれませんが、Bさんにとっては初めての出来事になってしまってるんですよね。
それと、「危ないから座ってて下さい。」・・・。転倒の危険性にばかり気をとられていて、Bさんがどうして歩き出したのか、その内面を理解しようとしない。
こんな対応はどうでしょう。
今日、初めて会ったような顔をして、「あらBさん、こんにちは。久しぶりですね。お元気でしたか?どちらまで行かれますか?」「ちょっとフラフラされていますが、大丈夫ですか?」「○○には、何の用事があるのですか?」「私もちょうどそちらへ向かう途中でしたので、ご一緒しましょう。」そう言って寄り添って歩く。
その場面だけをみれば、少し時間はかかるかもしれません。しかし、何度も同じ対応を繰り返す事に比べれば、お互い安定した気持ちで過ごす事ができ、結果的には効率的で効果的なケアができるはずです。
目の前の事象だけにとらわれず、認知症の方の世界観に寄り添う事を大切にした、そんな対応に心がけたいと思います。
斎田さん、コメントありがとうございます。全国で、思いを共有できる仲間がいることに共感・共鳴しました。
例で、出してくださった「転倒リスク者への声掛け」もそうですが、
毎日、全国各地の各施設で、同様のアシスト不足が発生しているとすれば、
もっともっと、寄り添い方をOJT方式で伝えていく必要がありますね。
アシスト不足を感じながらの「見逃し」や「あきらめ」が、一番怖いように思います・・・。
好ましいケアの終わりなき追求こそ、専門職が進むべき道ですよね。